| 前へ | |
| |
小林和作>エピソード | ||||
| |
|
||||
| |
終章・花を見るかな | ||||
| |
|||||
|
|||||
 |
|
昭和46年 9月 梅原龍三郎、中川一政、宮田重雄、里見勝蔵との合作画文集「美しき峯々の姿」を出版する。 十一月 勲三等旭日中綬章を受賞 和作83歳。 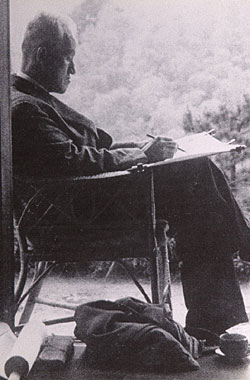 和作が自分自身についてこう語っている。
和作が自分自身についてこう語っている。
私はごくあたりまえの絵を描く画家でありたい。 昨日の画家でも困るが明日の画家でありたくもない。 私は芸術家ではなく民衆画家だ。 一般人向きの絵を数多く描いてそれを世間に放出し、 それによってえた金銭を広く民衆の役に立つように放出すればよいはずだから、却って有難い一面もある。 私が元来、まことに不器用な鈍才画家でかつ粗雑さを恥じないのです。 作品の上でも粗雑主義で押し通した鉄斎に少しは似ており、 鉄斎風かもしれないという自惚れているのです。(評伝238) このあたりが和作の芸術の本質かもしれない。 これほど広く民衆に敬愛された芸術家が、ほかに存在しただろうか。 確かに、和作は「花」を見ることの名人であった。 事実「花を見るから」の生涯であった。 それでも尚、中川一政が和作の遺作展のオープニングパーティーで語った一言が耳から離れない。 「和作さんは賑やかなことの好きな人でした。賑やかなことが好きなのは、根が淋しがり屋だったからでしょう。孤独だったんでしょうね」 孤独を愛した芸術家は多いが、和作は孤独を恐れる芸術家だったというのである。 和作をよく知ればこその言葉であろう。 たしかに、自分の在宅中は敏子夫人の外出を嫌うこと異常なほどの愛妻家であった。 写生旅行に同伴して、写生する傍で終始夫人に本を読ませていた和作、 夕方になると、人を恋うて街へ下り巷をさまよった和作、怖いほどの淋しさにはどんなに深い孤独が潜んでいたのであろう。(評伝241より抜粋) 昭和47年 6月、小林和作油絵展を尾道・おだ画廊で開き 「海」「秋山」など20点を出品する。
昭和48年 7月「広島県在住有名画家作品集」を自ら編集し、自費出版した。 この年、書を書きまくる。襖を張り替えれば天井一杯で書かせてもらうと周囲に宣伝したため、われ先に襖を張り替える家が続出。およそ200軒余の家の襖に書を書いてまわった。 第42回独立展に出品。(「春の海」)
11月3日広島県三次市方面にスケッチ旅行中(赤名峠を越すところ)、 自動車より降りる際に誤って転倒して頭を強く打ち、三次市双三中央病院に入院。 尾道から主治医らが駆けつけて最善の手当てをつくしたが、意識回復せぬまま翌4日午後9時10分、頭蓋骨内出血のため死去。 11月6日、自宅で密葬を営み、西国寺に葬る。 白菊に囲まれた遺影と遺作二点が飾られた式場には、地元近在から老若男女が集り、 和作が可愛がった小野耕之輔が、 生前の約束どおりビオラでフォーレの「夢のあとに」を演奏し、 つづいて和作の歌が尾道短期大学の合唱団らのコーラスで流れた。 龍膽の 花は冷めたき 秋の山に 人を恋うれど 日は沈むなり 行きゆきて 行きて盡きせぬ 絵の道を 今日は休みて 花を見るかな そして和作の好きだった藤圭子の「夢は夜ひらく」のレコードが流れると、 2千有余人の人々が生前の和作の面影に泣きに泣いた。 小林和作とは、そういう人であった。 
昭和50年 6月22日、尾道市西国寺境内に墓碑(梅原龍三郎筆)と筆塚(中川一政筆)が完成した。10月18日より11月9日まで広島県立美術館で「小林和作とその師友作品展」が開催され、小林関係143点と梅原龍三郎、中川一政、林武、小野竹喬など20点が展示された。 10月 第43回独立展に「山湖」一点が遺作として展示された。 昭和51年 2月「小林和作画集」が出版された。 この年、遺族から東京国立近代美術館へ「山湖」「海」の2点が寄贈された。 昭和52年 11月1日より12日まで、追想小林和作展―逝きて3年―が尾道・おだ画廊で開催れ、「島の春」「早春の山」など油絵、水彩25点が展示された。 昭和53年 2月から5月にかけて、小林和作遺作展が6箇所で開催され、初期の日本画3点と、春陽会、独立展などに発表の油絵72点のほか、水彩、漆絵、陶画など95点が展示された。 なお、11月4日の和作忌には、毎年、尾道のメインストリートのウインドウに和作忌協賛の絵が飾られる。(評伝225・年譜参照) |
|
||||
| |
||||
| |
||||
| |