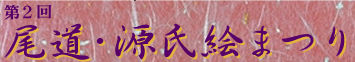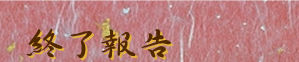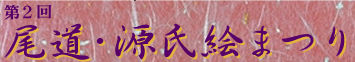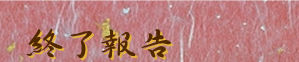| 表紙へ |
| 戻る |
原文
宵過ぐるほど、すこし寝入り給へるに、御枕上にいとをかしげなる女ゐて、「おのがいとめでたしと見奉るをば尋ね思ほさで、かくことなることなき人を率ておはして時めかし給ふこそ、いとめざましくつらけれ」とて、この御かたはらの人をかき起こさむとすと見たまふ。物に襲はるる心地して、おどろきたまへれば、灯も消えにけり。うたておぼさるれば、太刀を引き抜きてうち置き給ひて、右近を起こし給ふ。これも恐ろしと思ひたるさまにて参り寄れり。(新編全集一・164頁)
|
 |
| 空蝉物語と並行して、夕顔物語が展開します。乳母の病気を見舞った際、源氏は夕顔の花咲く宿の女性と歌のやりとりをします。絵はその場面を描いたものです。それが発端となって、いつしか源氏は夕顔の元に頻繁に通うようになります。この巻のクライマックスは、六条某院における夕顔との逢瀬の後、得体の知れぬ物の怪によって、夕顔が怪死する場面でしょう。灯が消えた闇の中、枕上に立った女は「おのが……」と口にしています。実はこの「おのが」は、いわば物の怪の用語ですので、そのおどろおどろしい雰囲気をくみ取って下さい。また「時めかす」「めざまし」
は、桐壷更衣のいじめにも登場した愛情表現でしたね。なお物の怪がどう描かれるかというと、近世の絵入り版本では、女性の髪を逆立てることでそれを表現しています。大和和紀の『あさきゆめみし』では、御息所の衣裳に蜘蛛の巣の文様を描くことで、物の怪であることを表出しています。つぼいこうの漫画では、瞳のない色抜きの姿で描かれています。皆それぞれに苦心しているようです。後に源氏は、夕顔が頭中将の愛人(常夏の女)であったことを確認しますが、そのことが玉鬘巻以降の玉鬘物語展開の伏線となっていることにも留意しておいて下さい。
|
|
●夕顔の席 煎茶・・・三癸亭賣茶流尾道支部
■お茶席は、書院にて。 |
詳しくはこちら |
|
 |
| 扇面の箇所をクリックすると、拡大してご覧になれます。 |
|
あらすじ
源氏十七歳
同じ頃、源氏にはひそかに通う年上の高貴な女性六条の御息所(みやすんどころ)(ずっと前に亡くなられた皇太子の妃)があった。そこへ通う途すがら、五条に住む乳母の病気見舞に立寄った。隣家に白い夕顔の花が咲いているのを見て、随身(ずいじん)に折って来るよう命じた。中から童女が出て来て「この蔓の花は扱いにくいのでこれに乗せて」と扇を差出した。源氏は扇面に散らし書きした歌を見て興味を覚え、乳母子(めのとご)の惟光に探
らせ、その手引きで通うようになった。
― この扇面の歌に「夕顔」が詠まれている ―
八月の十五夜に夕顔の宿に泊った源氏は、夜明け近くなってから、近くの廃院に女(夕顔)を連れ出した。その夜魔性の美しい女(六条の御息所の生霊)が枕頭に現れて夕顔を苦しめ急死させる。源氏は惟光の助けで葬送を済ませたが、二十日ばかり病
床に臥した。夕顔の侍女右近から聞くと、夕顔は雨夜の品定め(帚木の巻)で頭中将が語った隠 し妻で、北の方の嫉妬をおそれて身をかくした女であった。三歳になる娘もあると云う。右近はそのまま源氏の二条の院に仕えることになる。この頃、空蝉は、夫の伊予介と共に任地に下って行った。
|
|
|