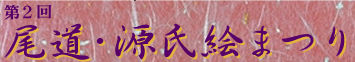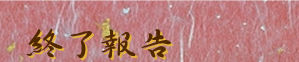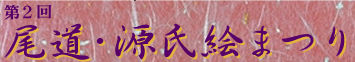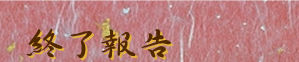平安時代、894年に菅原道真(すがわらのみちざね)の建議により遣唐使(けん とうし)が廃止されますと、今までの唐様の文化から和様化へと急速に、政治や文化
がより日本的なものへと生まれ変わってゆきました。 この文化の和様化の中で女性の衣服(朝服)も、その例にもれず寸法や様式が次第に変化してゆきます。
また、これら衣服の変化は、次のような要因が考えられます。
まず、儀式の座礼化進行です。 律令時代のはじめ宮廷の儀式は、大陸風立礼(立った姿勢で儀式を進行すること)で行われていましたが、大極殿をはじめとする宮中での儀式の場の炎上が度重なり、ついに再建されず、天皇の住まいである紫宸殿や清涼殿で、座った姿勢で儀式が進行するようになり、その結果座ったままで、威厳をただすことに適した衣服が要求されるようになりました。
さらに、貴族の住宅として「寝殿造」が現れます。 今日の京都御所や各神社に見られますが、蒸し暑く厳しい夏を快適に過ごせるようにと夏向きに建てられました。
その建物で逆に寒い冬を送るには、建具や家具では限度があり、自然に衣類によって暖をとりました。 いわゆる「重ね着」です。 寒い冬を送る為の生活の知恵が衣類の重着となりました。
この様な時代の要請から生まれたのが「十二単(じゅうにひとえ)や束帯(そくたい)」です。 柔らかな薄着を幾重にも着重ね、季節感あふれる美しい襲(かさね)の色目を豊かに演出する、唐衣裳とも云われる「十二単」がここに誕生したのです。
十二単は、公家女房の晴れの装いで、男子の束帯と共に宮中の正装として今日に及んでいます。 髪は垂髪(たれがみ)で、当時は髪の長いのが美人の要素の一つとして考えられておりました。
眉は抜いて描き、白粉、頬紅、口紅をつけ、歯は黒く染めました。
衣服の構成は、唐衣(からぎぬ)、裳(も)、表着(うわぎ)、打衣(うちぎ)、袿(うちき・五枚重ねた時は、後に五衣(いつつぎぬ)と云われる)、単(ひ
とえ)、紅(あか)の打袴(うちばかま:若年、未婚のものは濃色)からなりたち、持物は衵扇(あこめおうぎ)《檜扇(ひおうぎ)》・帖紙(たとう)を手にしておりました。
裳を付けてから唐衣をつける例と、唐衣の背に裳の大腰を当てる例とが あります。 |
|