
中 国 新 聞
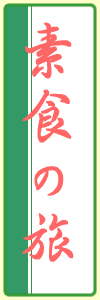
| ◆◆
真剣勝負の 仕事場の記憶 ◆◆ |
 川田さんの祖父や父がかゆに混ぜ、 「ごちゃ」と呼んで食べた「はったい粉」
|
■広島県神辺町の川田平八郎さん(四六)は昭和二十九(一九五四)年、三重県名張市の生まれ。十三歳の時、製鉄所の技術者として神辺町に移り住んだ祖父と父につき従った。祖父は日本刀の研ぎ師。父もその後継者。しかし自身はと言うと、「徒弟制度についていけませんでした。これからは違う、と鼻で笑っていました」と振り返る。
■祖父も父も仕事場に入る時に必ずすることがあった。身を清め、神棚に手を合わせる前に「ごちゃ」を食べる。麦こがし粉、はったい粉のことであり、三重の山間部では「ごちゃ」と言った。
■祖父や父は満足のゆく仕事ができた時、おかゆに「ごちゃ」を入れ、おかゆの粘りを増して食べた。「かゆにごちゃ入れとくれ」の声に母は安どした顔をしたという。
■一般の家庭では「ごちゃ」に砂糖を少し混ぜ、熱湯をかけて練る。おやつの「ごちゃガキ」は、この中にカキを刻んで入れ、甘さを出した。ちょっと裕福な家庭ではお茶ではなく、粉ミルクか牛乳を入れていた。
■川田さん方では「ごちゃ」は仕事前の儀式。子どもは食べることができなかった。祖父も父も仕事場では何も話さない。なのに何種類もある砥石(といし)が正確に出てくる。その姿は背中にも目があるようだった。
■父が足をけがした。祖父が出先から電話で「足をけがしなかったか。ワシの足が痛いぞ」。仕事が終わっても親子には戻らない。父を怒っても褒めることはしない。川田さんは父をいじめるなと祖父に子どもながら訴えたが、「お前もごちゃ食うてからもの言え」。
■祖父は九十六歳で他界し、父は七十四歳で隠居した。孫を呼んでは「お父さんには『ごちゃ』のつくり方教えてないからなぁ、へたでなぁ」。
■刃物は硬いと折れる。だが、軟らかくすると曲がりやすい。「折れず、曲がらず、よく切れる」という三つの要素を満たすのは調和。その調和を極めるのは理屈や理論ではないらしい。徒弟制度を拒んだ川田さんも今は「もし、子どもが祖父や父の道に進むのであれば応援したい」と語っていた。