
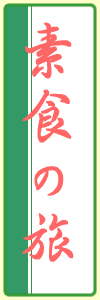
| ◆◆
宮大工の息抜き 遠い昔 ◆◆ |
 遠い昔の手の傷のしょうゆの痛み思う 「卵かけご飯」
|
■明治四一(一九〇八)年、大阪府堺市生まれの藤岡仙太郎さん(九三)は、五十九歳で宮大工を辞めた。百人の心を一つにまとめるが棟りょうの器。「百論一つに止めるの器量なき者は慎みおそれて匠の長の座を去れ」。自分の不徳を恥じず、弟子たちの意見をまとめることが出来きなくなった時だ。
■六年前に八十六歳で死去した師匠西岡常一さんから口伝を受けた言葉に従い、引退を決意した。「弟子をどついてばかりや。何やってもアホとボケしか言いませんでしたわ。自分にゆとりがなかったんでしょうな」。
■その後、京都で農業を営み、親類の住む笠岡市に移り住んで十五年がたつ。今は米をつくる農家だが、庭で飼っている鶏の卵も自慢の一つだ。
■藤岡さんは十一歳の時から宮大工の基礎を祖父から体で教わっていた。一日と十五日が休みで、その前の日が給料日。休みの日には神棚にお神酒を上げて、堺の港の船員食堂で卵かけご飯を食べるのが楽しみだった。わずかだが、お給金をもらっていた。当時は卵かけご飯一杯で素うどん十杯食べることができた。
■熱い丼飯に卵。しょうゆに加え、山椒(さんしょう)の実といった七味でつくる「黒七味」と呼ばれる、やたら辛いそれをかけるのが楽しみだった。食べながら技を伝授してくれる祖父の言葉も耳には入らなかった。
■槍鉋(やりがんな)で手を切った休みの日。食堂に出かけ、いつもの卵ご飯を頼んだその時、しょうゆを手の傷にかけたのだ。「あの痛みは今も覚えていますね。今の人には信じがたいが、しょうゆには殺菌効果があったんですわ。確かにあの時うんでいました」。
■藤岡さんの鶏は自生している草と虫を食べている。その卵を手にしながら、「百論一つに止めるの器量なき者は・・・」と念仏のような言葉が聞こえてきた。今回の芸予地震が来た時、一番に考えたのは七十年前に建てた京都の小さなお堂が無事かどうかだったという。