
中 国 新 聞
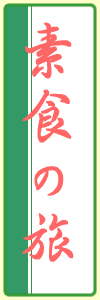
| ◆◆
厚み増して 実感した平和 ◆◆ |
 季節や労働に応じて 塩や酢を あんばいしてきた日の丸弁当
|
■衣料切符三十点で木綿の反物一反が配給された戦時中。家族は男衆の衣服をつくり、家族は男衆の古着をつぎはぎして着る。「男は家を出ると、何があるか分からないから・・・」。三原市宗郷町の熊本幸子さん(七三)もそんな時代を生きた。
■戦時中の台所はなべとかましかなく、数枚の取り皿がぜんに並ぶだけ。三菱重工関連の現場で働いていた夫は昼は日の丸弁当を食べ、夜はイモのつるの皮をはぎ、フキのように煮た「煮しめもどき」を家族と食べる。
■しかし、男衆すべてが満足に弁当を食べていた訳ではない。降り積もった雪をサッと詰め、お米が入っているように見せかけていた人もいた。
■「父はタバコを吸いませんでした。配給のタバコを鞆の漁師さんに上げるのです。そしたらお礼に私たちの船にタイが飛び込んできました」。何軒かが協力し、漁の傍ら配給品の物々交換でしのいだ時代のことだ。
■敗戦から高度経済成長に時代に向かう十年間、薄っぺらな日の丸弁当がだんだん厚くなる。それにおかず一品が付いた時、やっと胸をなで下ろした。そんな日の丸弁当にも意外な技があった。
■「月中だから少し入れといたよ」「暑そうだからちょっとばかり多めにしといてくれよ」。月中は大変な作業が多く、ご飯に小さじ軽く一杯の塩をいつもより多く振りかける。夏は腐らないように少し酢を振りかけ、水っぽい梅干しを選ぶ。
■弁当の底はご飯を詰め込み、中間を軽く押さえて上は詰め込む。ふたでお茶を飲み、空になった弁当箱をまくらに次の仕事に備えてひと寝入り。早朝、父や夫に弁当の厚みを感じながら手渡した幸子さんは「お金があっても、お米がない時代もあったのです・・・」。忘れてはいけない言葉だ。
写真 ・ 文 村上宏治
©2001 中国新聞 ・ 村上宏治 All rights reserved